
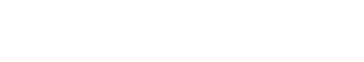
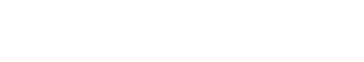
災害が発生した時の「備え」はお済みですか?
いつ起こるかわからない災害に備え、灯り、水、食料、トイレ、情報などあらゆるものに対して常日頃から意識をし被害をより小さくとどめる「減災」について考えることが重要です。 給水車や炊き出しなどの「公助」「共助」が行き渡るまでに、自分たちで生き抜く「自助」をいかに行うか、そのためには何が必要か。ミドリ安全は、食べやすい保存食(非常食)、防災ヘルメット、家具転倒防止などの災害避難グッズや防災セットなど、豊富な防災グッズを取り揃えています。家庭や職場で本当に必要な防災グッズについて考え、その日に備えましょう。
災害時すぐに持ち出せる「防災セット」や「非常用品」は、いざという時に備えておくと安心です。家庭用なら、保管場所に合う大きさのものや最低限揃えたいものなど、企業向けであればエレベーターに置けるものやコンパクトに設置できるものがおすすめです。また、車載できるものや帰宅支援に必要な防災グッズも選びましょう。
災害で避難をする際に体を守るためにご家庭や施設で備蓄できるおすすめのグッズです。災害時は落下物から頭を守ったり床に飛散したものから足を守る必要があります。
非常食は高カロリーで栄養バランスがよいものを選びましょう。保存食の備えは、定期的に食べる事で賞味期限切れを防ぐローリングストック法がおすすめです。
災害時用のトイレや毛布、寝袋などの寝具、衛生用品が必要です。コンパクトなものや使用後の保管量を減らせるものなどを備蓄しましょう。
自然災害発生時に安否確認といった情報収集・人命救助・避難誘導をするために必要な用品など、災害時の対策本部におすすめのグッズを紹介しています。
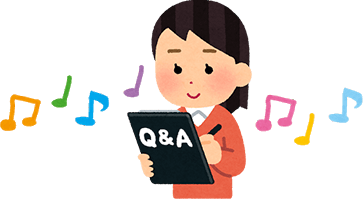

災害はいつ起こるかわかりません。「いざ」という時のために、災害後の救助や救援物資の到着までに最低限必要なものを準備しておきましょう。
携:常に携帯しておくもの 持:避難時に持ち出しするもの 備:自宅や会社に備蓄しておくもの
| 貴重品 | |
|---|---|
| 現金 携 持 | 紙幣だけではなく硬貨も用意 |
| 車や家の予備鍵 持 | 鍵を紛失した際に予備があると安心 |
| 眼鏡・コンタクト 携 持 | コンタクトは(予備も)長時間使用できないので眼鏡は必須 |
| 銀行口座契約番号 携 持 | 通帳を紛失した場合、口座番号と本人確認が必要 |
| 健康保険証 携 持 | 万が一の体調不良時にいつでも病院に行けるように |
| 身分証明書 携 持 | 運転免許証・パスポートなど |
| 印鑑 持 | 停電などでATMが使えなくなる場合があるため |
| 母子健康手帳 持 | 避難時、何かあった時にすぐ提示できるよう準備 |
| 情報収集 | |
|---|---|
| 多機能ラジオ 持 | 予備電池も必須。手回し充電がおすすめ |
| 携帯電話 携 | 充電器・モバイルバッテリーも用意 |
| 家族の写真 持 | 家族とはぐれてしまった時の確認用に |
| 緊急時の連絡先 携 | 自宅以外でも数か所連絡が取れる所の番号を |
| 広域避難地図 持 | 道路が通行止めの際の迂回路や避難場所の確認などに |
| 筆記用具 携 持 | 情報や連絡先などのメモを取ったり、伝言を残す際に |
| 保存食 | |
|---|---|
| ご飯類 持 備 | 美味しくて簡単にできる防災用ご飯 (3日分備蓄) |
| めん類・餅 持 備 | 簡単にできる防災用麺類・餅など (3日分備蓄) |
| おかず 持 備 | 温めなくても手軽に簡単!防災用おかず (3日分備蓄) |
| スープ・ジュース 持 備 | 具材たっぷり!野菜不足の時におすすめ (3日分備蓄) |
| ビスケット・クッキー 持 備 | 色々な種類を揃えておいた方が飽きがきません (3日分備蓄) |
| パン 持 備 | しっとり高カロリー。ゴミも配慮したエコパッケージ (3日分備蓄) |
| 保存水 持 備 | 保管場所と容量を検討し分散保管を (1日1人3リットル) |
| 生活用品 | |
|---|---|
| 防災用ヘルメット 持 備 | 折りたたみ用ヘルメットは保管・携帯しやすくて便利 |
| ランタン・懐中電灯 持 備 | 予備電池も必須。手回し充電などであれば電池不要 |
| 防犯ブザー 携 持 | 音で居場所を知らせるために |
| 使い捨てカイロ 携 持 | 防寒対策や保温用に |
| 保温用品 携 備 | シート・ブランケットなど |
| 簡易衛生マスク 携 持 | 防寒対策やウイルス対策としても使える |
| 真空パック毛布 持 備 | 軽量でコンパクトに収納可能 |
| 寝具 持 備 | 家族の人数分用意する |
| スリッパ 持 | 避難所などでの上履き用に |
| 軍手・手袋 持 | 素手では危険が伴うので、革製など丈夫な作業手袋は必須 |
| 非常用給水袋 持 | 水を運んだり蓄えたりするのに便利 |
| レインウェア 携 持 | 雨天時以外にも防寒対策として |
| 長靴 持 | 雨天時や足場の悪い場所で |
| ブルーシート 備 | 敷物代わりや間仕切りなど、様々な用途で使える |
| 非常用トイレ 持 備 | 災害時のトイレ対策は必須 |
| テント 備 | 避難所代わりにも。プライペートも確保できる |
| 万能ナイフ 携 持 | ハサミ・ナイフ・缶切りなど複合ツールが便利 |
| ビニール袋 持 備 | 大小、様々なサイズが複数枚あると良い |
| マッチかライター 持 | 暖房器具への点火などに |
| 救急・衛生 | |
|---|---|
| 救急用品 備 | 消毒薬・脱脂綿・ガーゼ・ばんそうこう・包帯・三角巾など |
| 衛生用品 持 備 | 歯ブラシ・洗顔・体ふき・除菌シートなど |
| 常備薬・持病薬 持 | 体調不良時に備えて。お薬手帳や処方箋のコピーも |
| タオル 持 | 応急処置や火災時に口を抑えたりと様々な用途で使える |
| トイレットペーパー 備 | トイレ以外でも様々な用途で使える |
| 着替え 持 | 家族の人数分3日分程度準備。下着も忘れずに |
| ウエットティッシュ 携 持 | 手が洗えない時や水が無い時に重宝する |
| 生理用品 携 持 | 傷の手当やガーゼの代わりにもなる |
| 子ども向け | |
|---|---|
| 紙おむつ 備 | 5〜7日分は備蓄しておくと良い |
| 粉ミルク・哺乳瓶 持 | 5〜7日分は備蓄しておくと良い |
| 離乳食 持 | 5〜7日分は備蓄しておくと良い |
| 携帯カトラリー 持 | 非常時には何かと重宝します |
| お尻ふき 持 | 5〜7日分は備蓄しておくと良い |
| 携帯用お尻洗浄機 持 | ― |
| ネックライト 持 | 暗い所や灯りのない所でハンズフリーで使えます |
| 抱っこひも 持 | 小さい子どもがいる家庭では必需品です |
| 子どもの靴 持 | 子どもの足元もしっかり守るために |
| 女性向け | |
|---|---|
| 紙おむつ 持 備 | 5〜7日分は備蓄しておくと良い |
| 生理用品 持 | 5〜7日分は備蓄しておくと良い |
| おりものシート 持 | 5〜7日分は備蓄しておくと良い |
| サニタリーショーツ 持 | ― |
| 中身の見えないゴミ袋 持 | ゴミ袋以外でも何かと使えます |
| 防犯ブザー 持 | 災害時でも自分の身を守りましょう |
| ホイッスル 持 | 避難誘導の際にあると便利 |
| 高齢者向け | |
|---|---|
| 大人用紙パンツ 持 備 | 5〜7日分は備蓄しておくと良い |
| 生理用品 持 | 5〜7日分は備蓄しておくと良い |
| 杖 持 | 特に災害時は足元が悪くなっているので注意して使用しましょう |
| 補聴器 持 | ― |
| 介護食 持 | 5〜7日分は備蓄しておくと良い |
| 入れ歯・洗浄剤 持 | ― |
| 吸水パッド 持 | 5〜7日分は備蓄しておくと良い |
| デリケートゾーンの洗浄剤 持 | ― |
| 持病の薬 持 | 5〜7日分は用意しておくと良い |
| お薬手帳のコピー 持 | 5〜7日分は備蓄しておくと良い |